【放牧 始め方】放牧の前の必須事項「馴致」とは?
「放牧を始めたいけれど、どうやって牛を外に出せばいいの?」というお問い合わせは、よくいただくお問い合わせの一つです。
実は、いきなり放牧をすると家畜にとって大きなストレスになり、健康や生産性に悪影響を及ぼすこともあります。
今回は、放牧の前の「馴致」に関する基礎的な情報と抑えておくべきポイントをご紹介します。

草地などの広い場所でのびのびと放牧するイメージが一般的かもしれませんが、
家畜の種類や頭数、放牧できる草地面積や人員などの条件によって、そのスタイルは様々です。
 生まれて間もない哺乳・哺育期の家畜は、畜舎(ちくしゃ)と呼ばれる建物の中で過ごします。
生まれて間もない哺乳・哺育期の家畜は、畜舎(ちくしゃ)と呼ばれる建物の中で過ごします。
運動がてら外に出ることはあるかもしれませんが、多くの時間は畜舎の中で大切に飼育されます。
そのため、いきなり長時間外にだすと、大きなストレスを抱えてしまう可能性があります。
さらに、餌が変化することも要因です。
多くの場合、人間が干し草やトウモロコシなどの飼料を与える「舎飼い(しゃがい)」と呼ばれるスタイルが一般的です。
放牧になると、これまでとは違った新鮮な青草(牧草)を食べるため、餌の変化に追いつけず、採食がうまくいかないケースがあります。
放牧を始めて間もないころはよく観察を行い、徐々に慣らしながら、放牧をはじめるのが良いでしょう。
 前述した通り、急激な変化にさらされると、家畜はかえってストレスを抱えてしまいます。
前述した通り、急激な変化にさらされると、家畜はかえってストレスを抱えてしまいます。
はじめは短い期間からスタートして、徐々に慣らしていきましょう。
パドックのような少し狭い面積からスタートすると、家畜の様子を管理しやすいメリットもあります。
電気柵は家畜が触れて、電気ショックを受けることで警戒心が生まれ、近づいたり脱柵しないよう警戒心ができることで効果があります。
一緒に電気柵を学習した個体と放牧させると学習が早まります。
その他製品は >>>こちら
 家畜の様子をしっかりと管理しましょう。
家畜の様子をしっかりと管理しましょう。
特に群れで放牧する場合は、仲間外れにされたり、体調を崩している個体がいないかや、蹄が伸びすぎていないかなど、よく観察しておきましょう。
 頭数に対して牧区が狭すぎると、草が短くなりすぎたり裸地が進みやすくなります。
頭数に対して牧区が狭すぎると、草が短くなりすぎたり裸地が進みやすくなります。
逆に頭数が少なすぎると、草が伸びすぎて消化しづらい硬い草になったり、株化が進んでしまいます。
特に放牧すると、舎飼のときよりもエネルギーを消費しやすくなるので、草の品質管理は重要になります。
また、スタッフ間でも共通のルールや対応マニュアルをまとめておけると、スムーズになります。
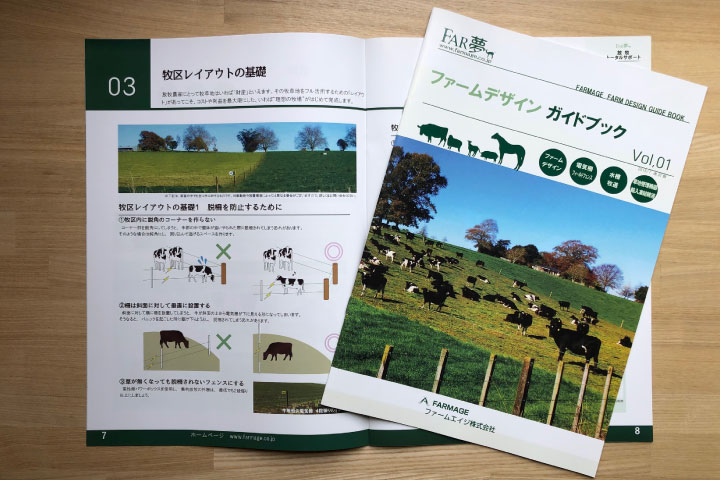
詳細はこちら>>>放牧デザインカタログ

詳細はこちら>>>NZ北海道酪農協力プロジェクト

実は、いきなり放牧をすると家畜にとって大きなストレスになり、健康や生産性に悪影響を及ぼすこともあります。
今回は、放牧の前の「馴致」に関する基礎的な情報と抑えておくべきポイントをご紹介します。
目次
1.放牧とは
牛や羊などの家畜を畜舎(ちくしゃ:家畜が生活する施設)ではない環境で飼うことを意味します。
草地などの広い場所でのびのびと放牧するイメージが一般的かもしれませんが、
家畜の種類や頭数、放牧できる草地面積や人員などの条件によって、そのスタイルは様々です。
2.なぜ?放牧の前に「馴致」が必要?
 生まれて間もない哺乳・哺育期の家畜は、畜舎(ちくしゃ)と呼ばれる建物の中で過ごします。
生まれて間もない哺乳・哺育期の家畜は、畜舎(ちくしゃ)と呼ばれる建物の中で過ごします。運動がてら外に出ることはあるかもしれませんが、多くの時間は畜舎の中で大切に飼育されます。
そのため、いきなり長時間外にだすと、大きなストレスを抱えてしまう可能性があります。
さらに、餌が変化することも要因です。
多くの場合、人間が干し草やトウモロコシなどの飼料を与える「舎飼い(しゃがい)」と呼ばれるスタイルが一般的です。
放牧になると、これまでとは違った新鮮な青草(牧草)を食べるため、餌の変化に追いつけず、採食がうまくいかないケースがあります。
放牧を始めて間もないころはよく観察を行い、徐々に慣らしながら、放牧をはじめるのが良いでしょう。
3.失敗しないため!馴致のために抑えておくべきポイント
3-1.短い期間から始める
 前述した通り、急激な変化にさらされると、家畜はかえってストレスを抱えてしまいます。
前述した通り、急激な変化にさらされると、家畜はかえってストレスを抱えてしまいます。はじめは短い期間からスタートして、徐々に慣らしていきましょう。
パドックのような少し狭い面積からスタートすると、家畜の様子を管理しやすいメリットもあります。
3-2.電気柵の学習(馴致)
電気柵を使って放牧する場合、電気柵の学習(馴致)が必要です。一緒に電気柵を学習した個体と放牧させると学習が早まります。
参考商品
その他製品は >>>こちら
3-3.家畜の行動や健康状態をしっかりと管理
 家畜の様子をしっかりと管理しましょう。
家畜の様子をしっかりと管理しましょう。特に群れで放牧する場合は、仲間外れにされたり、体調を崩している個体がいないかや、蹄が伸びすぎていないかなど、よく観察しておきましょう。
3-4.草地の管理
 頭数に対して牧区が狭すぎると、草が短くなりすぎたり裸地が進みやすくなります。
頭数に対して牧区が狭すぎると、草が短くなりすぎたり裸地が進みやすくなります。逆に頭数が少なすぎると、草が伸びすぎて消化しづらい硬い草になったり、株化が進んでしまいます。
特に放牧すると、舎飼のときよりもエネルギーを消費しやすくなるので、草の品質管理は重要になります。
3-5.緊急時の対応ルールにしておく
ゲリラ豪雨や異常気象などが発生した際に、すぐに放牧地から退避させるなどルールを確認しておきましょう。また、スタッフ間でも共通のルールや対応マニュアルをまとめておけると、スムーズになります。
4.その他 お役立ち情報
4-1.牛舎飼いから放牧に切り替えた由仁町の酪農家のドキュメンタリー(馬場牧場の事例)
北海道由仁町の放牧酪農家 馬場敏さんに密着し、舎飼いから放牧酪農に切り替えた理由、放牧のメリットや学んだこと、農業に携わる方へのメッセージをいただきました。放牧酪農家を志す人々を応援します
4-2.放牧デザインカタログ
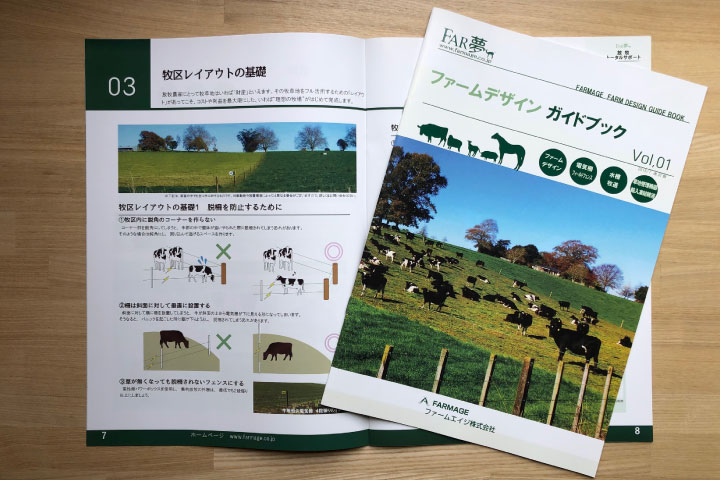
放牧のメリットを最大限に引き出すために、最も基本となる部分を要約した一冊です。放牧地の柵だけでなく、草地改良から牛群改良、牧道やゲートの配置に至るまで、これから放牧に取り組む方はもちろん、既に取り組んでいただいてる方にも、ご自身の牧場を見直す気づきのきっかけになるかと思います。
詳細はこちら>>>放牧デザインカタログ
4-3.NZ北海道酪農協力プロジェクト ウェブセミナー(録画・記事)

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取組で、北海道とホクレンが協力しています。
放牧における牧草地の利用効率と酪農経営の採算性向上を目的として、平成26 年8月から2年間のプロジェクトとして開始した後、道内4地域の調査対象農家の追跡調査を行うため、プロジェクトを平成30 年3月まで延長しました。
その後2戸の調査対象農家を対象としたフォローアップ調査・実証、オンラインセミナーの開催など放牧普及を実践する取組です。
詳細はこちら>>>NZ北海道酪農協力プロジェクト
5.まとめ

放牧は、家畜の健康増進だけでなく、エサ代の削減や管理する人間の手間も軽減できます。
しかし、いきなり外に出すのではなく、段階的に「馴致」を行うことが成功のカギとなります。
放牧を始めたいと考えている方は、まず「馴致」の重要性を理解し、段階的なステップを踏んで実践していきましょう。
お客様のスタイルや各地の放牧導入事例をもとに、弊社スタッフがアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
全国送料無料でお届け!まずは資料請求からはじめてみる






